※本記事はプロモーションが含まれています。

レジン作品を美しく仕上げる上で、避けては通れないのが気泡の問題です。この記事では、初心者の方にも分かりやすくレジン作品の気泡の抜き方について、原因から具体的な対処法までを網羅的に解説します。そもそも気泡が入らない方法はあるのか、もし硬化後でも修正できるのか、といった疑問にもお答えします。
さらに、気泡抜きにエンボスヒーターは有効なのか、身近なドライヤーで気泡抜きはできますか?といったよくある質問にも触れ、爪楊枝やチャッカマンを使った方法、さらには放置したり湯煎で温めたりする方法まで、様々なアプローチを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
- レジンに気泡が入る原因と予防策
- 爪楊枝などを使った基本的な気泡の消し方
- 専用ツールや代用品を使った効果的な対処法
- 硬化後に気泡を見つけた際のリカバリー術
基本的なレジン気泡の抜き方と予防策
- レジンに気泡が入る主な原因とは
- まずは試したい気泡が入らない方法
- 気泡の抜き方は爪楊枝でつぶすのが基本
- レジンの気泡の抜き方で放置は有効?
- レジンの気泡が硬化後に入っていたら
レジンに気泡が入る主な原因とは

レジン作品に気泡が入ってしまう原因は、一つだけではありません。主に3つのパターンが考えられ、それぞれの原因を理解することが、気泡を防ぐための第一歩となります。
1つ目は、レジン液をボトルから出す際に空気が混入するケースです。これは特に粘度の高いレジン液で起こりやすく、比較的大きな気泡ができます。ボトルの上部に溜まった空気が、液を押し出す際に一緒に巻き込まれてしまうことが原因です。
2つ目は、レジン液と着色剤などを混ぜ合わせる際に発生するケースです。スティックなどで勢いよく混ぜると、その動きが空気を巻き込み、無数の細かい気泡ができてしまいます。一度細かくなった気泡は取り除くのが非常に難しくなるため、注意が必要です。
3つ目は、封入する素材に付着している空気が原因となるケースです。ドライフラワーやシェル、ビーズといった素材の表面や細かな凹凸には、目に見えない空気がまとわりついています。これらをレジン液に沈めると、付着していた空気が気泡となって現れるのです。
気泡の主な原因
気泡は「液を出すとき」「混ぜるとき」「素材を封入するとき」の3つのタイミングで発生しやすいと覚えておきましょう。
これらの原因を知ることで、どの工程で特に注意深く作業すべきかが見えてきます。次の項目では、これらの原因を踏まえた上で、そもそも気泡を作らないための予防策を解説します。
まずは試したい気泡が入らない方法

気泡ができてから抜く作業も大切ですが、最も効率的なのは、そもそも気泡が入りにくくする方法を実践することです。特に、自分でコントロールしやすい「混ぜる工程」での工夫は、作品のクオリティを大きく左右します。
最大のポイントは、「とにかくゆっくり混ぜること」に尽きます。レジン液と着色剤などを混ぜ合わせる際、焦って早くかき混ぜてしまうと、多くの空気を巻き込んでしまいます。さらに、勢いよく混ぜることで、既にある気泡を分裂させてしまい、より小さく除去しにくい気泡を増やしてしまう原因にもなります。
泡立て器でメレンゲを作る時をイメージしてみてください。空気をたくさん含ませるために勢いよく混ぜますよね。レジンでは、その逆を意識することが大切です。空気を入れないように、静かに、優しく混ぜることを心がけてみてください。
また、レジン液をボトルから出すときも、勢いよく出すのではなく、容器の縁に沿わせるように静かに注ぐと、気泡の発生を抑制できます。開封直後のレジン液は、ボトル上部に空気が溜まっていることが多いです。そのため、使用前にキャップを閉めたままボトルの口を下に向け、斜め45度くらいに傾けてしばらく置いておくと、空気が上部に移動し、液を出す際の気泡混入を減らすことができます。
これらの地道な工夫が、後の気泡取りの作業を格段に楽にしてくれます。
気泡の抜き方は爪楊枝でつぶすのが基本

レジン液の中に気泡ができてしまっても、焦る必要はありません。特に、比較的大きな気泡であれば、身近な道具を使って簡単につぶすことができます。最も手軽で基本的な方法が、爪楊枝や竹串の先端で気泡を物理的に潰すことです。
やり方は非常にシンプルで、気泡の膜を優しく突くだけです。プチっと音を立てて気泡が消えていきます。もし、気泡がうまく潰れずに分裂してしまったり、側面に移動してしまったりした場合は、爪楊枝の先で気泡をすくい取るようにして取り除くか、型の外に追い出すように誘導しましょう。
ウッドスティックやスパチュラも便利
ハンドメイド用のウッドスティックや、先端がヘラ状になった調色用スパチュラなども非常に便利です。爪楊枝は木製のため、それ自体に含まれる空気が新たな気泡の原因になる可能性がゼロではありません。その点、金属製やプラスチック製のスパチュラであれば、その心配なく作業に集中できます。
この方法はコストがかからず、誰でもすぐに試せるのが最大のメリットです。ただし、あまりにも小さい気泡を一つひとつ潰していくのは根気がいる作業になります。また、粘度の高いレジン液だと、気泡が移動しにくく、うまく潰せないこともあります。あくまで「大きめの気泡に対する初期対応」と位置づけ、他の方法と組み合わせて使うのがおすすめです。
レジンの気泡の抜き方で放置は有効?

「気泡は放置しておけば自然に抜ける」という話を聞いたことがあるかもしれません。これは半分正しく、半分は注意が必要です。
結論から言うと、時間を置くことで一部の気泡は自然に浮き上がってきて表面で消えます。レジン液を型に流し込んだ直後は、内部に多くの気泡が混在しています。この状態で硬化を急がず、数分から数十分ほど平らな場所に置いておくと、液の中をゆっくりと気泡が上昇し、表面に達したものは自然に弾けて消えることがあります。
この方法は、特に粘度が低いサラサラしたタイプのレジン液でより効果的です。また、軽く容器の底をトントンと優しく叩いて振動を与えると、気泡が浮き上がるのを助けることができます。
放置だけでは全ての気泡は抜けない
注意点として、この方法で抜けるのは、あくまで浮き上がりやすい比較的大きな気泡や、表面近くにある気泡に限られます。素材の隙間に入り込んだ頑固な気泡や、粘度の高い液に閉じ込められた微細な気泡は、放置するだけでは抜けきらないことがほとんどです。
したがって、「放置」は気泡を減らすための一つの有効な工程ではありますが、これだけで完璧に気泡をなくせるわけではないと理解しておくことが重要です。放置して浮き上がってきた気泡を、前述の爪楊枝などで潰す作業と組み合わせることで、より効果的に気泡を除去できます。
レジンの気泡が硬化後に入っていたら

細心の注意を払っていても、硬化させた後に作品の内部に気泡が残っていることに気づくのは、レジン作りでよくあるケースです。一度完全に硬化してしまったレジンの内部にある気泡を、完全になかったことにするのは非常に難しいですが、リカバリーする方法は存在します。
主な修正方法は、「削って、再度レジンでコーティングする」というアプローチです。
まず、気泡がある箇所まで、紙やすりや精密ヤスリを使って慎重に削っていきます。このとき、粗い番手のヤスリから始め、徐々に細かい番手のものに変えていくと、表面を滑らかに仕上げやすくなります。気泡が完全に露出し、穴が開いた状態になったら、削りカスを綺麗に拭き取ります。
次に、その穴を埋めるように、上から新しいレジン液を少量流し込みます。この際、新たな気泡が入らないように、爪楊枝などを使って丁寧にレジン液を穴に行き渡らせるのがコツです。その後、再度UV-LEDライトで硬化させます。最後に、作品全体の表面をコーティング用のレジン液で薄く覆って再度硬化させると、削った跡が目立たなくなり、艶のある仕上がりに戻ります。
硬化後の修正は難易度が高い
この方法は手間と技術が必要であり、完璧に元通りにするのは簡単ではありません。削りすぎると作品の形が変わってしまったり、再コーティングがうまくいかず段差ができてしまったりするリスクも伴います。硬化後の修正は最終手段と考え、できる限り硬化前に気泡を取り除くことを目指しましょう。
道具別レジンの気泡の抜き方と注意点
- 気泡抜きはエンボスヒーターが確実
- ドライヤーで気泡抜きはできますか?
- 気泡をチャッカマンで消す際の注意点
- 気泡の抜き方として湯煎も選択肢に
- スポイトで気泡を吸い取る方法
気泡抜きはエンボスヒーターが確実

レジン作品の気泡処理において、爪楊枝で潰したり、時間を置いて浮かせたりする方法も有効ですが、「手早く、かつ確実に、プロのような仕上がりを目指したい」場合に最もおすすめなのがエンボスヒーターを使用する方法です。これ一つで、これまで苦労していた微細な気泡の処理が劇的に楽になります。
エンボスヒーターとは?その仕組み
エンボスヒーターは、本来スタンプアートなどでインクを熱で盛り上げる「エンボス加工」に用いられるクラフト用の道具です。ドライヤーと似ていますが、風量が弱く、約250℃の高温な熱風をピンポイントで吹き出すことに特化しています。
この高温の熱風をレジン液に当てると、主に2つの効果で気泡が消えていきます。
- 粘度の低下:レジン液が温められることで、一時的に粘度が下がりサラサラの状態になります。これにより、内部に留まっていた気泡が浮き上がりやすくなります。
- 空気の膨張:気泡内部の空気が熱によって膨張し、体積を増すことで浮力が強まり、最終的に表面で弾けて消滅します。
爪楊枝では処理しきれないような無数の細かい気泡も、この仕組みによって面白いくらい綺麗になくなるため、作品の透明度とクオリティを格段に向上させることが可能です。
失敗しないエンボスヒーターの選び方
エンボスヒーターは様々なメーカーから販売されていますが、選ぶ際には以下のポイントをチェックすると良いでしょう。
- 温度と風量:レジン用としては、高温・弱風のモデルが最適です。多くのクラフト用ヒーターはこの仕様になっています。
- ノズルの形状:先端が細いものは、よりピンポイントに熱を当てやすく、細かい作業に向いています。
- 自立スタンドの有無:作業後、高温になったノズルを安全に冷ますために、本体を立てて置けるスタンドが付いていると非常に便利です。
- 静音性:夜間に作業することが多い方は、作動音の静かさも選ぶ基準の一つになります。
定番は「清原(KIYOHARA)」のエンボスヒーター
多くのハンドメイド作家に愛用されているのが、清原(KIYOHARA)社のエンボスヒーターです。使いやすさと安全設計に定評があり、これから購入を検討している方には特におすすめのモデルです。
実践!エンボスヒーターの正しい使い方
エンボスヒーターの使い方は非常にシンプルですが、効果を最大化し、安全に使用するためのコツがあります。
- 安全の確保:まず、十分な換気を行い、作業台には耐熱性のマットなどを敷きましょう。
- 適切な距離を保つ:ヒーターの先端を、レジン液の表面から5cm~10cmほど離して構えます。
- 動かし続ける:スイッチを入れ、同じ箇所に熱を当て続けないように、常にゆっくりと円を描くか、左右にスライドさせるように動かします。
- 気泡が消えたら止める:数秒当てると、気泡がスッと消えていくのが見えます。全ての気泡が消えたら、速やかにスイッチを切りましょう。
使い方のワンポイントアドバイス
熱を当てすぎると、レジン液が必要以上にサラサラになり、モールドの隅々まで行き渡りやすくなるという副次的な効果もあります。ただし、長時間当てすぎると硬化不良や変質の原因になるため、「短時間で、まんべんなく」を常に意識してください。
知っておきたい注意点とメリット・デメリット
非常に便利なエンボスヒーターですが、使用する上での注意点も理解しておくことが大切です。メリットとデメリットを以下の表にまとめました。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ◎ 微細な気泡まで根本的に除去できる | △ 購入するための初期コストがかかる |
| ◎ 作業効率が劇的に向上する | △ 電源がない場所では使用できない |
| ◎ 非接触なので作品の表面を傷つけない | △ モデルによっては作動音が気になる |
| ◎ 表面張力が働き、ツヤが出やすくなる | △ 熱に弱い素材(モールド等)を変形させるリスク |
高温による変形や火傷に注意
エンボスヒーターの熱は非常に高温です。プラスチック製のフレームや、一部の安価なシリコンモールドに長時間熱を当てると、変形や変質の原因となる可能性があります。また、使用直後の金属ノズルは非常に熱くなっているため、火傷には絶対に注意してください。必ずスタンドを使い、お子様やペットの手の届かない場所で冷ますようにしましょう。
本格的にレジン作品の制作を続けるのであれば、エンボスヒーターは「買ってよかった」と思えるツールの筆頭です。初期投資はかかりますが、それ以上に作品のクオリティアップと時間短縮という大きなリターンが期待できますよ。
ドライヤーで気泡抜きはできますか?

エンボスヒーターの代用品として、家庭にある「ドライヤー」を使えないかと考える方は多いかもしれません。しかし、結論から言うと、ドライヤーでの気泡抜きは基本的におすすめできません。
その理由は、エンボスヒーターとドライヤーの機能的な違いにあります。エンボスヒーターが「弱い風で高温の熱」を出すことに特化しているのに対し、ドライヤーは「強い風で髪を乾かすための適度な熱」を出すことを目的としています。この「風の強さ」が、レジンにとっては大きな問題となるのです。
ドライヤーの風をレジン液に当てると、気泡が消える前に、その風圧でレジン液が型の外に飛び散ってしまったり、せっかく配置したパーツが動いてしまったりする可能性が非常に高いです。これでは、気泡を消すどころか、作品自体を台無しにしてしまいかねません。
以下の表で、両者の違いを比較してみましょう。
| 比較項目 | エンボスヒーター | ドライヤー |
|---|---|---|
| 主な目的 | 熱を加えること | 風で乾かすこと |
| 温度 | 高い(約250℃) | 比較的低い(最高140℃程度) |
| 風量 | 弱い・ピンポイント | 強い・広範囲 |
| レジンへの適性 | ◎(最適) | ×(非推奨) |
このように、ドライヤーはレジンの気泡抜きには不向きです。もし代用品を探すのであれば、他の方法を検討することをおすすめします。
気泡をチャッカマンで消す際の注意点

エンボスヒーターがない場合の代用策として、ライターやチャッカマンの炎をさっと通す、という方法も紹介されることがあります。これは、炎の熱によって気泡を表面で弾けさせるという原理で、確かに気泡を消す効果はあります。
しかし、この方法は大きな危険を伴うため、実行する際には最大限の注意が必要です。最も注意すべき点は、火災のリスクです。レジン液は可燃性ではありませんが、作業台に敷いた紙や、近くにあるアルコール類などに引火する可能性があります。必ず周囲に燃えやすいものがないかを確認し、換気を十分に行う必要があります。
また、炎をレジン液に近づけすぎたり、当てる時間が長すぎたりすると、レジンが焦げて黄色く変色してしまったり、ススが入ってしまったりする恐れがあります。あくまで「一瞬、表面を撫でるように」炎を通すのがコツですが、この加減は非常に難しく、初心者の方には特におすすめできません。
チャッカマン使用の危険性
- 火災のリスク:周囲の可燃物に引火する危険性があります。
- 作品の劣化:レジンが焦げたり、ススが入ったりする可能性があります。
- 火傷のリスク:自身の火傷にも十分注意が必要です。
安全性を最優先に考え、できる限りエンボスヒーターなど、より安全な道具を使用することを強く推奨します。
気泡の抜き方として湯煎も選択肢に

熱を利用して気泡を抜きやすくするという点では、「湯煎」も有効な方法の一つです。これは、エンボスヒーターのように硬化直前のレジン液に熱を加えるのではなく、使用前のレジン液そのものを温めるアプローチです。
レジン液は、温められると粘度が下がり、サラサラの状態になります。粘度が低くなると、液内部での気泡の移動がスムーズになり、自然に抜けやすくなるのです。また、混ぜる際の空気の巻き込みも少なくなります。
湯煎の具体的な方法
やり方は簡単です。まず、お湯を張った容器を用意します。お湯の温度は、熱すぎるとレジンの品質に影響を与える可能性があるため、50℃〜60℃程度の、お風呂より少し熱いくらいが目安です。そこに、キャップをしっかりと閉めたレジン液のボトルを浸け、数分間温めます。
ボトルが温まり、レジン液がサラサラになったら、通常通りに作業を始めます。この方法であれば、着色剤と混ぜる段階から気泡が入りにくくなり、もし気泡が入っても抜けやすいため、作業が非常にスムーズになります。
特に冬場など、気温が低くレジン液が硬くなっている場合に効果的な方法です。ただし、温めたレジン液は硬化反応が少し早まることがあるため、作業は手早く行うように心がけましょう。
スポイトで気泡を吸い取る方法

爪楊枝で潰すには小さすぎるけれど、たくさん集まっていて目立つ。そんな微細な気泡の塊には、「スポイト」を使って吸い取ってしまうという方法が有効です。
クラフト用の精密なスポイトや、100円ショップなどで手に入る化粧品用のスポイト、あるいはお弁当用の醤油入れなどでも代用できます。先端を気泡が集まっている箇所に近づけ、気泡ごとレジン液を少量吸い取ります。
この方法のメリットは、小さな気泡を物理的に、かつ確実に取り除ける点です。特に、パーツの隙間など、爪楊枝の先端が入りにくい場所にある気泡を除去するのに役立ちます。
力加減には注意が必要
ただし、この方法には少しコツが必要です。力を入れすぎて一気に吸い込んでしまうと、レジン液も一緒に大量に吸ってしまい、作品の表面に大きなへこみや穴ができてしまいます。ゆっくりと、気泡だけを狙うように慎重に吸い取る力加減が重要です。
吸い取ってへこんでしまった部分は、新しいレジン液を少量足して平らにならしてから硬化させましょう。他の方法と組み合わせることで、より完璧に近い仕上がりを目指すことができます。
最適なレジンの気泡の抜き方を見つけよう:まとめ

最後にレジンの気泡の抜き方のリストを載せています。レジンの気泡対策に役立ててみてください。

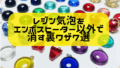

コメント