※本記事はプロモーションが含まれています。
レジン作品のクオリティを格段に引き上げる「色付け」。市販されている専用の着色剤も非常に便利ですが、「手元にある画材で、もっと気軽にオリジナルカラーを作れないだろうか?」と考えたことはありませんか?この記事では、そんなクリエイターの探求心に応えるべく、レジンを絵の具で色付けする際のあらゆる疑問や不安を解消します。
例えば、そもそもレジンにアクリル絵の具は使えますか?という基本的な問いから、レジンが絵の具で固まらない、あるいはレジンとアクリル絵の具がダマになるといった、誰もが一度は経験するかもしれない失敗の原因と、それを科学的に解決するための具体的な対策まで詳しく解説します。
さらに、レジンとアクリル絵の具を分離させないプロの混ぜ方のコツ、レジンと水彩絵の具を使ってガラスのような透明感を出す方法も紹介します。応用編として、レジン着色剤の代わりになるものはあるのか、レジン着色に使えるものを100均で探すヒント、UVレジンはポスカで着色できるのか、といったテクニックまで網羅。レジンに絵の具を混ぜるとどうなるのか、その化学的な側面から実践的なコツまで、全てがこの記事で明らかになります。
- レジンに使える絵の具と使えない絵の具の科学的な違い
- 絵の具が原因で起こる硬化不良や分離を根本から解決する方法
- 100均アイテムなど身近なもので着色を代用する際の注意点とコツ
- 絵の具でレジン着色を成功させ、作品の表現力を高めるための鉄則
レジンの色付けを絵の具で行う基本と主な失敗例
- そもそもレジンにアクリル絵の具は使えますか?
- レジンに絵の具を混ぜるとどうなるか解説
- レジンが絵の具で固まらない時の主な原因
- なぜレジンはアクリル絵の具でダマになるのか
- レジンとアクリル絵の具を分離させないコツ
- レジンと水彩絵の具の相性と安全な使い方
そもそもレジンにアクリル絵の具は使えますか?

結論から申し上げますと、レジン製作に特定の絵の具を使用することは可能です。しかし、絵の具と一口に言っても多種多様で、全ての絵の具がレジンに適しているわけではありません。それぞれの絵の具が持つ化学的な特性と、使用するレジンの種類(UVレジンか2液性エポキシレジンか)との相性を理解することが、成功への第一歩となります。
UVレジンは紫外線(UV-LEDライトなど)のエネルギーを利用して硬化する「光硬化樹脂」であり、一方の2液性エポキシレジンは主剤と硬化剤という2つの液体を混ぜ合わせることで化学反応を起こし硬化する「化学硬化樹脂」です。この硬化メカニズムの違いが、使用できる絵の具の種類を大きく左右します。
ここでは、代表的な絵の具の種類と各レジンとの相性、そしてその理由を詳しく解説した表を以下に示します。
| 絵の具の種類 | UVレジンとの相性 | エポキシレジンとの相性 | 特徴と化学的注意点 |
|---|---|---|---|
| アクリル絵の具 | ◎ 使用可能 | ◎ 使用可能 | 顔料とアクリル樹脂で構成。乾燥後は耐水性になるためレジンとの馴染みが良い。ただし、顔料が光を遮るため、入れすぎは硬化不良の最大の原因となります。表面塗装が最も安全です。 |
| 水彩絵の具 | △ 注意が必要 | △ 注意が必要 | 主成分が水分と顔料のため、レジンの化学反応を著しく阻害します。特にUVレジンでは硬化不良を高確率で引き起こします。使用する場合は、硬化後の表面への着色に限られます。 |
| 油絵具 | × 使用不可 | ○ 使用可能 | 油分がUVレジンの光重合反応を阻害するため、全く硬化しない、あるいは著しく硬化が遅れる原因となります。化学反応で硬化するエポキシレジンであれば少量混ぜ込めますが、硬化時間は通常より長くなる傾向があります。 |
この表から分かるように、最も手軽で汎用性が高いのはアクリル絵の具です。ただし、どの絵の具を利用するにしても「レジン液の総量に対して、着色剤は1%以下に留める」という基本原則を念頭に置くことが、あらゆる失敗を回避するための絶対条件となります。
レジンに絵の具を混ぜるとどうなるか解説

レジン液に絵の具を混ぜるという行為は、精密に設計された化学反応のシステムに、予期せぬ「添加剤」を入れることと同じです。本来、レジン液は主成分であるオリゴマーやモノマー、そして光重合開始剤などが最適なバランスで配合されており、それ自体で完結するよう設計されています。ここに絵の具という異物が混入すると、主に2つの物理的・化学的な問題を引き起こす可能性があります。
1. 硬化阻害(Curing Inhibition)
UVレジンは、特定の波長(主に365nm〜405nm)の紫外線を吸収することで、光重合開始剤が活性化し、連鎖的な重合反応(硬化)が始まります。大手レジンメーカーである株式会社パジコの公式サイトでも、UV-LEDライトでの硬化原理が解説されています。しかし、アクリル絵の具などに含まれる「顔料」の粒子は、この紫外線を吸収または散乱させる性質を持っています。絵の具の混入量が多すぎると、顔料の粒子が壁のように紫外線の行く手を阻み、レジン液の内部、特に深部まで光エネルギーが到達しなくなります。その結果、表面だけが薄く硬化し、内部は未硬化のままという、最も典型的な「硬化不良」が発生するのです。
2. 分離・色ムラ(Separation & Uneven Color)
水と油が混ざり合わないように、物質にはそれぞれ親和性があります。レジン液(油性寄り)と、水分を多く含む水彩絵の具は、界面張力の違いから均一に混ざり合うことができず、時間経過と共に分離してしまいます。また、アクリル絵の具であっても、顔料の粒子の比重がレジン液と異なる場合、硬化するまでの間に顔料が沈降したり、逆に浮き上がったりして色ムラの原因となります。これを防ぐには、顔料がレジン液中に均一に分散した状態を保つための、丁寧な攪拌(かくはん)技術が不可欠です。
絵の具を混ぜる潜在的リスク
絵の具の混入は、硬化不良だけでなく、完成したレジン作品の長期的な安定性にも影響を与える可能性があります。例えば、レジン本来の透明度が損なわれたり、経年による変色(黄変)が促進されたり、物理的な強度が低下したりすることが考えられます。アクセサリーなど、耐久性が求められる作品や、販売を目的とした作品を制作する際には、品質が保証されたレジン専用着色剤の使用を強く推奨します。
レジンが絵の具で固まらない時の主な原因

「UVライトを長時間当てているのに、表面のベタつきが取れない」「モールドから出したら中身が液体だった」といった硬化不良は、絵の具を使ったレジン着色で誰もが直面しうる最大の壁です。この原因は、99%以上が「光エネルギーの不足」、すなわち光の透過不足にあります。
前述の通り、UVレジンは紫外線の力で硬化する化学プロセスです。ここに光を遮断する顔料、特に黒色や白色、濃い赤色、メタリックカラーなどの不透明な色を多く混ぜると、顔料の粒子が紫外線を吸収・乱反射してしまい、レジン液の深部まで有効なエネルギーが届かなくなります。特に黒色は全ての波長の光を吸収するため、最も硬化不良を起こしやすい色と言えます。
硬化不良を科学的に防ぐ3つの対策
- 絵の具の添加量を厳守する: 着色の基本は「つまようじの先にほんの少し付ける」ことから始め、レジン液の透明感が辛うじて残る程度で調整します。着色剤の添加量は、レジン液の総重量に対して最大でも1%以内、できれば0.5%以下に抑えるのが安全です。
- 積層法(Layering Method)を実践する: 濃い色や不透明な色合いにしたい場合、一度に厚く流し込むのは絶対に避けるべきです。厚さ1〜2mm程度の薄い層を作り、一度硬化させます。その上に次の層を重ねて再び硬化させる、という作業を繰り返す「積層法」を用いることで、各層に確実に紫外線を届かせ、完全硬化させることができます。
- 照射エネルギーを最適化する: 通常のクリアレジンよりも照射時間を1.5倍〜2倍程度長めに設定しましょう。また、使用するUVライトのワット数や波長も硬化速度に影響します。可能であれば、モールドを裏返したり、側面から光を当てたりすることで、光が届きにくい部分を補い、全体の硬化を促進させることが重要です。
特に、底が深いシリコンモールドや、色の濃いモールドを使用する場合、光がさらに届きにくくなるため、より一層慎重な硬化作業が求められます。
なぜレジンはアクリル絵の具でダマになる?

均一に混ぜたつもりでも、硬化した作品を光に透かすと、色の小さな粒やモヤモヤとしたダマが残っていることがあります。これは、レジン液とアクリル絵の具の化学的な相性が完璧ではないために起こる、顔料の「凝集(agglomeration)」という現象が主な原因です。
大手画材メーカーのターナー色彩株式会社の解説によると、アクリル絵の具は色の元である「顔料(Pigment)」と、それを固着させる接着剤の役割を持つ「アクリルエマルション(アクリル樹脂)」から構成されています。このアクリルエマルションがレジン液の主成分(アクリレートモノマー等)と混ざり合う際に、完全には溶解せず、顔料の粒子同士が再び集まって小さな塊(ダマ)を形成してしまうのです。
特に、絵の具を一度にたくさん投入すると、局所的に絵の具の濃度が高い部分ができ、混ざりきる前に凝集が始まってしまいます。これを防ぐには、少量ずつ加えて、その都度丁寧に分散させるという地道な作業が最も効果的です。また、古いアクリル絵の具は内部で成分が分離・硬化し始めている場合があり、ダマの原因となりやすいため、なるべく新しいものを使用することをおすすめします。
補足:絵の具の「透明(Transparent)」と「不透明(Opaque)」
専門的なアクリル絵の具のチューブには、色の名前と共に「透明(Transparent)」や「半透明(Semi-Transparent)」、「不透明(Opaque)」といった透明度が記載されていることがあります。これは使用されている顔料の光透過性を示しています。もし透明感を活かした作品を作りたいのであれば、「透明(Transparent)」と表記された絵の具を選ぶと、顔料の粒子が元々細かく光を透過しやすいため、レジン液にも比較的きれいに馴染み、ダマになりにくい傾向があります。
レジンとアクリル絵の具を分離させないコツ

レジン液とアクリル絵の具がうまく混ざらず、分離や色ムラが起きてしまうのは、両者の性質が根本的に異なるためです。しかし、正しい道具選びと丁寧な混合作業によって、この問題を解決することができます。美しい着色作品を作るための、プロも実践する分離させないコツを段階的に解説します。
ステップ1:道具を準備し、絵の具を少量加える
まず、作業の土台となる道具を整えましょう。おすすめは、内側が滑らかで底が浅いシリコン製の調色パレットです。汚れが落ちやすく、繰り返し使えるだけでなく、混ぜる際の様子が確認しやすいのが利点です。
パレットにレジン液を適量注いだら、いよいよ絵の具を加えます。ここが最初の重要なポイントです。
絵の具は「ごく微量」から始める
つまようじの先端にほんの少しだけ絵の具を付け、それをレジン液に「なすりつける」ようなイメージで加えます。チューブから直接レジン液に出すのは、量が多すぎて失敗の元になるため絶対に避けましょう。最初は「色が薄いかな?」と感じるくらいが適量です。
ステップ2:「練り込む」ように混ぜ合わせる
絵の具を加えたら、次は混ぜる工程です。ここでのキーワードは「かき混ぜる」のではなく「練り込む」です。
調色スティック(シリコン製や金属製のものがおすすめ)を使い、以下の手順で丁寧に作業を進めます。
- まず、絵の具とレジン液が接している部分を、スティックの先端で優しく潰すようにして馴染ませます。
- 次に、パレットの底に絵の具を押し付けるようにしながら、スティックをゆっくりと動かし、顔料の塊を砕いていくイメージで練り込んでいきます。
- 「の」の字を描くように、パレットの底や側面についたレジン液もこまめにこすり取りながら、全体を均一にしていきます。
この「練り込み」作業を丁寧に行うことで、顔料の粒子がレジン液中に細かく分散し、分離やダマのない、なめらかなカラーレジン液が完成します。
注意:混ぜすぎによる気泡
色が均一になったら、それ以上混ぜ続けるのはやめましょう。必要以上に混ぜ続けると、空気を巻き込んでしまい、気泡が大量に発生する原因となります。気泡が入らないよう、終始ゆっくりとした動作を心がけてください。
ステップ3:気泡を取り除き、状態を確認する
均一に混ざったように見えても、内部には微細な気泡が残っていることがあります。モールドに流し込む前に、最後の仕上げを行いましょう。
ここでワンポイントアドバイスです!
混ぜ終わったカラーレジン液を、エンボスヒーターやドライヤーの温風でさっと温めると、レジンの粘度が一時的に下がり、気泡が表面に浮き上がってきて消えやすくなります。ただし、温めすぎは厳禁です。レジンの急な硬化や変質を招くので、あくまで「軽く表面を撫でる」程度にしてくださいね。
気泡を取り除いたら、スティックでレジン液を少量すくい上げ、光に透かしてダマや分離がないか最終確認します。ここで問題がなければ、モールドやフレームに静かに流し込みましょう。この一連の丁寧な作業が、分離や色ムラのない美しい仕上がりへと繋がります。
レジン液の気泡抜きに関しての記事はこちらになります。参考にしてみてください!
>>レジンの気泡の抜き方|原因別の消し方と道具まとめ
>>レジン気泡抜きはドライヤーでOK?正しい使い方とコツ
レジンと水彩絵の具の相性と安全な使い方

水彩絵の具は、その名の通り主成分の多くが「水分」であるため、レジン液に直接混ぜ込むのには最も不向きな画材と言えます。レジン(特にUVレジン)の硬化反応は、水分によって著しく阻害されるため、高確率で硬化不良(ベタつき、硬化しない等)を引き起こしてしまいます。
しかし、その特性を逆手に取り、直接混ぜ込むのではなく、「硬化したレジンの表面に塗装し、さらにその上からコーティングする」という技法を用いることで、水彩絵の具ならではの淡く、滲むような透明感のある独特の表現が可能になります。これは、他の着色方法では再現が難しい、繊細なニュアンスを作品に与えるテクニックです。
水彩絵の具を使った表面着色の手順
- 土台の作成: まず、透明なレジンで作品の土台となる形を作って、完全に硬化させます。この時、表面に未硬化のベタつきが残らないよう、しっかりと硬化させることが重要です。
- 表面への着色: 硬化したレジンの表面に、水で溶いた水彩絵の具で色を塗ります。水彩画を描くように、滲みやグラデーション、ぼかしといった技法を自由に活かすのがポイントです。
- 完全な乾燥: 着色後、絵の具が完璧に乾燥するまでじっくりと待ちます。ここでの乾燥が不十分だと、後のコーティング時に絵の具が溶け出し、作品が台無しになります。ドライヤーの冷風を遠くから当てるなどして、水分の蒸発を促しましょう。
- レジンによる再コーティング: 絵の具が完全に乾いたことを確認したら、上から透明のレジンを薄く、気泡が入らないように丁寧に塗り広げ、再度硬化させます。これにより、水彩の色彩がレジンの中に封じ込められ、保護されます。
この手順を守れば、硬化不良のリスクなく、水彩絵の具の美しい風合いをレジン作品に取り入れることができます。特に、100円ショップなどで手に入る固形タイプの水彩絵の具(水彩パレット)は、発色も良く、この技法に手軽に挑戦できるためおすすめです。
代用品は?レジンの色付けするための絵の具の応用術
- レジンで絵の具の透明感を表現する方法
- レジン着色剤の代わりになるものはある?
- レジン着色に使えるもの【100均編】
- UVレジンはポスカで着色できる?
- 成功の鍵!レジン 色付け 絵の具の鉄則
レジンで絵の具の透明感を表現する方法

レジン作品の最大の魅力の一つである、光が透き通るような「透明感」。顔料系の絵の具を使うと、どうしても色が濁り、この透明感を損ないがちです。しかし、いくつかのコツと工夫を凝らすことで、絵の具を使いながらもクリアで美しい色合いを作り出すことが可能です。
最も効果的で失敗が少ないのは、前項で詳しく解説した水彩絵の具を使った表面着色テクニックです。硬化した透明なレジンのキャンバスに水彩で色を付け、その上からさらに透明なレジンで封じ込めることで、色がレジンの層の中に浮かんでいるように見え、ガラス細工や七宝焼のような独特の奥行きと透明感が生まれます。
アクリル絵の具で透明感を出すには?
アクリル絵の具で透明感を目指す場合、まず試すべきは画材店などで入手できる「リキッドタイプ」や「インクタイプ」のアクリルカラーです。これらは通常のチューブ入り絵の具よりも顔料濃度が低く、サラサラとした液体状であるため、レジン液にも比較的均一に混ざりやすく、透明度を保ちやすい特徴があります。
もう一つのテクニックは、通常のアクリル絵の具であっても、「色が付いているか分からない」と感じるくらい、ごくごく微量をレジン液に混ぜることです。爪楊枝の先端で触れる程度の量を丁寧に練り込むことで、レジン本来の透明度をほぼ維持したまま、ほんのりと色づいたカラークリアレジンのような表現が可能になります。この方法で複数の色を準備し、マーブル模様や宇宙塗り(ギャラクシー)のグラデーションを作る際にも応用できる、非常に有効なテクニックです。
レジン着色剤の代わりになるものはある?

専用のレジン着色剤が手元になくても、私たちの身の回りには着色の代わりになるアイテムが意外と多く存在します。ただし、これらは本来の用途とは異なるため、メリットとデメリットをよく理解した上で使用することが重要です。ここでは、代表的な代用品とその特徴を表にまとめました。
| 代用品の種類 | カテゴリ | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| アイシャドウ・チーク | 粉末 | パールやラメ感が美しく、入手しやすい。コスメの再利用にもなる。 | 油分が多い製品は硬化不良の原因になることがある。粒子が粗いと混ざりにくい。 |
| パステル | 粉末 | カッターで削って使用。ふんわりとしたマットな質感が出せる。混色も容易。 | 湿気を吸いやすいため、保管に注意が必要。入れすぎると透明感が完全になくなる。 |
| トナー(プリンター用) | 粉末 | 非常に粒子が細かく、少量で鮮やかに発色する。 | (非推奨)成分が不明で、健康への影響やレジンの経年劣化を招くリスクがある。 |
| マニキュア | 液体 | ラメやパール、ホログラムなど種類が豊富で、独特の質感が得られる。 | 溶剤成分がレジンと反応し、分離や気泡、硬化不良を起こしやすい。上級者向け。 |
| 油性マーカーのインク | 液体 | インク芯から直接インクを抽出し、アルコールインクアート風の表現が可能。 | インクのアルコール成分が完全に揮発しないと硬化不良の原因になる。 |
代用品を使用する際の共通の注意点
これらの代用品は、あくまで「本来の用途とは違う使い方」であることを常に念頭に置いてください。制作直後は美しく見えても、時間経過と共に予期せぬ変色や、レジンの劣化を引き起こす可能性は否定できません。特に、友人へのプレゼントや販売用の作品を制作する際には、品質の安定性が保証されたレジン専用の着色剤を使用することを強く推奨します。
レジン着色に使えるもの【100均編】

「高価な道具を揃える前に、まずは手軽にレジン着色を試してみたい」という方にとって、100円ショップ(100均)はまさにアイデアの宝庫です。近年ではレジン関連商品そのものが充実しており、多くのレジン作家が100均アイテムを上手に活用して素晴らしい作品を生み出しています。ここでは、着色に使える代表的な100均アイテムをいくつかご紹介します。
最近の100均の進化は本当に目覚ましいですよね! レジン液やモールドはもちろん、ネイルアート用のパーツやクラフト素材など、着色に応用できるアイテムが驚くほど充実しています。私も新しい発見がないか、定期的にパトロールしていますよ。
(【公式】ダイソーネットストア)(【公式】《1個からお届け》Can★Doネットショップ)
1. 固形水彩絵の具(水彩パレット)
画材コーナーにあるこのアイテムは、100均着色アイテムの王様と言っても過言ではありません。前述の通り、硬化したレジンの表面に着色し、その上からコーティングする方法で大活躍します。ラメ入りのカラーが含まれたパレットもあり、これ一つで表現の幅がぐっと広がります。
2. アイシャドウ・チーク
コスメコーナーは、キラキラとした着色料の宝庫です。特にパール感が強いものや、大粒のラメが入っているものは、レジン液に少量混ぜるだけで、専用のパール顔料にも劣らないゴージャスな輝きを放ちます。チップやブラシでモールドの内側に直接色を擦り付けてからレジンを流し込む、という面白いテクニックにも使えます。
3. パステル
画材コーナーや文具コーナーにあるパステルも、着色剤として非常に優秀です。カッターナイフなどで慎重に削って粉末状にし、レジン液に練り込みます。顔料濃度が高いため、ごく少量でマットで柔らかい雰囲気の、マカロンのような可愛らしい色合いを作りたいときに最適です。
これらのアイテムを組み合わせることで、専用の着色剤を一つも持っていなくても、わずかな投資で無限に近いカラーバリエーションを楽しむことが可能になります。
こちらの動画では、100円ショップで手に入る水彩絵の具を使った着色の具体的な手順が紹介されており、レジン作品の制作に役立ちます。
【レジン 着色】100均水彩絵の具でできるか実験!その結果は?!Part.2◇coloring resin
100均のレジン液に関して情報はこちらの記事がおすすめです。ぜひ覗いてみてください!
>>ダイソーのレジン液300円は高品質?口コミと使い方を徹底解説
UVレジンはポスカで着色できる?

プラバン作りやデコレーションで絶大な人気を誇る三菱鉛筆のサインペン「ポスカ(POSCA)」も、工夫次第でレジン着色に応用することが可能です。ただし、他の絵の具と同様に、レジン液に直接インクを混ぜ込むのは、インクの溶剤成分が硬化を阻害する可能性があるため推奨できません。
ポスカを最も安全かつ効果的に使う方法は、硬化したレジンの表面や、プラバンなどで作った封入パーツに直接文字や絵を描き、それをコーティングするというものです。ポスカの公式サイトでは、そのインクが「乾いた後は水に流れず、重ね描きも可能」な水性顔料インクであることが明記されており、この優れた耐水性と固着性が、レジンコーティング前の描画に非常に適しているのです。
ポスカを使った着色・描画の手順
- レジンやプラバンで作成した、完全に硬化した土台を用意します。
- 土台の上に、ポスカで好きなイラストやメッセージを自由に描きます。
- インクが完全に乾くまで、焦らずしっかりと時間を置いて乾燥させます。乾燥が不十分なまま次の工程に進むと、上からレジンを塗った際にインクが溶け出し、滲みや混色の原因になります。
- インクの乾燥を指で触れて確認した後、上から透明のレジン液を気泡が入らないように静かにコーティングし、UVライトで硬化させます。
レジンの硬化面は非常に滑らかで、ポスカのインクを弾いてしまうことがあります。その場合は、スポンジやすり(400番〜600番程度)で表面を軽くサンディングして微細な傷を付ける(「足付け」と言います)か、模型用のプライマー(下地剤)を薄く塗布すると、インクの定着が劇的に向上します。
成功の鍵!レジンの色付けを絵の具で行うための鉄則

この記事で解説してきた、絵の具を使ってレジンの色付けを成功に導くための最も重要なポイントを、最後にリスト形式で総まとめします。これらの鉄則を守ることが、失敗のリスクを最小限に抑え、あなたの作品のクオリティを最大限に高めるための鍵となります。

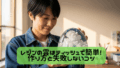

コメント